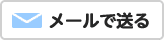マンガ家が作品を発表するのに、経験豊富なマンガ編集者の存在は重要だ。しかし誰にでも“初めて”がある。ヒット作を輩出してきた優秀な編集者も、成功だけではない経験を経ているはず。名作を生み出す売れっ子編集者が、最初にどんな連載作品を手がけたのか──いわば「担当デビュー作」について当時を振り返りながら語ってもらい、マンガ家と編集者の関係や、編集者が作品に及ぼす影響などに迫る連載シリーズだ。
今回は「ダーウィン事変」(うめざわしゅん)をはじめ、「コンプレックス・エイジ」(佐久間結衣)、「とんがり帽子のアトリエ」(白浜鴎)、「天国大魔境」(石黒正数)、「カオスゲーム」(山嵜大輝)などを手がけるアフタヌーン編集部の寺山晃司氏が登場。2009年に講談社に入社し、週刊現代編集部を経てモーニング編集部へ。モーニング・ツー編集長を経て、現在は月刊アフタヌーンの副編集長を務めている。壮大なスケールのサイエンスフィクションやサスペンスアクションから、摩訶不思議な世界を克明に描写するファンタジー、人間の心のひだを1枚ずつ描写するような繊細な人間ドラマまで、幅広い作品を世に送り出している編集者だ。
大学院の修士課程までバリバリの理系(専門はウシガエルの脳!)ということも関係してか、こちらのQに対するAがバシッと明確で気持ちいい。合理的な問題解決能力で磨き上げてきた編集手法に触れながら、歩んできた仕事人生を語ってもらった。
取材・文 / 的場容子
コロコロとボンボンで育ち、黒田硫黄で「アフタヌーン体験」
1983年生まれの寺山氏の子供時代は、マンガやゲームに囲まれていた。
「『お小遣いはくれなくてもいいから、代わりにコロコロとボンボンを両方買ってほしい』という子供でした。アニメから『ドラえもん』を知り、原作マンガを小学校に上がる前から読み始め、『ドラえもん』が載っているマンガ雑誌があるらしいぞということでコロコロを買い、横に似たような雑誌があるなという理由でボンボンを買って……という流れです。
『ドラえもん』の影響は大きかったです。映画のもとになった『大長編』シリーズを見つけて読んでみたり、『パーマン』やSF短編集を読んだり。マリオとロックマンも好きで、コロコロで連載していた『スーパーマリオくん』(沢田ユキオ)や、ボンボンのシリアスめな『スーパーマリオ』シリーズ(本山一城)を楽しみにしていました。さらに、同時期にボンボンで読んでいた『王ドロボウJING』(熊倉裕一)というマンガが、自分は今でもすごく好きで。ボンボンの中ではどちらかというと大人向けのマンガで、セリフとか絵の描き方がすごくおしゃれで、『こんなマンガがあるんだ!』とすごくびっくりしたのを覚えています」
「王ドロボウJING」は、1995年からコミックボンボンで連載されていた作品。なんでも盗む“王ドロボウ”のジンと、その相棒のキールが大活躍する冒険譚で、独特の作り込まれた世界観と映画のようにキザなセリフ回しで、今なお根強い人気を誇るマンガだ。話題を先取りするのであれば、寺山氏がアフタヌーン作品を好きになる萌芽がここにあったのかもしれないと思わせる作風だ。中学生になると、ジャンプを読み始めた。
「自分が読み始めた時期は、ちょうど『ONE PIECE』(尾田栄一郎)や『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)、『SHAMAN KING』(武井宏之)が始まったあたりで、『これは面白いぞ』と。『ONE PIECE』の1巻を初版で買ったのをよく覚えています。そこから高校生になって、大人向けのマンガにも興味が出てきて、アフタヌーンを読むように。一度、高校の友達が黒田硫黄さんの『茄子』を貸してくれたことがあったのですが、当時の自分では何が描いてあるのかが全然わからなくて。ただ、読んでいてすごい気持ちがいい。だけどそれを言語化できない。『マンガでわからないことってあるんだ!』と、自分の読解力が足りないことがすごく悔しかったですね。そのときに改めて、マンガって面白いなと実感しました」
まさに「アフタヌーン体験」。黒田硫黄の「茄子」もまた、アフタヌーンのオルタナティブな色を象徴するような作品だ。このように、寺山氏の人生の傍らには常にマンガがあった。ほかに、アフタヌーンでは「蟲師」(漆原友紀)が好きだったという。
「漆原さんのサイン会に行ったりしていました。今でもサインは大事に取って置いています。大学に行くとさらにコアなマンガが好きになって、アックスを読むようになりました」
当時も現代も、マンガ好きやサブカル好きが行き着く極北がアックスではないだろうか。1998年から青林工藝舎が出しているマンガ誌で、根本敬や花くまゆうさく、鳩山郁子、近藤ようこ、本秀康らが執筆。伝説的マンガ誌・月刊漫画ガロ──白土三平の「カムイ伝」を掲載し、水木しげる、内田春菊、みうらじゅん、蛭子能収らが活躍していた──の後継誌と言える。現在も隔月誌として刊行を続けている。
ウシガエルの脳→週刊現代→モーニング!?
一方、大学は理系の学部に進学し、修士課程まで進んだ寺山氏。修士課程の研究テーマは、「ウシガエルの脳」だった。
「自分はもともと理系で、理科、とくに生物の先生になりたかったんです。教育学部の理学科に入って教員免許を取ろうとしていたのですが、子供に教えるのは向いていないことに気づきました。どうも子供を相手にするのが得意ではなくて、自分に教えられる生徒はかわいそうだなと思いまして(笑)」
マンガ編集者という仕事を意識したのは、就職活動を始めてからだったという。
「研究室に残って生物学の研究を続けていたのですが、修士課程で就職活動を始め、最初は食品会社の研究職などを志望していました。ただ、そこで働いている方の話を聞いたときに、自分が働いているイメージがあんまり湧いてこなかった。選考も通らないですし、どうしたものかと思ったときに、ふっと自分の部屋の本棚にマンガがたくさんあることを思い出しました。マンガは描けないけど、マンガ編集者という仕事はあるぞ。マンガに関われるなら面白いかもしれない、と。それで、自分の本棚を見たときに一番多かったのが講談社のマンガだったので、講談社を受けました」
見事内定を獲得し、2009年に講談社に入社した寺山氏は、マンガの編集部ではなく、まず週刊現代に配属となった。
「毎年、週刊誌には新卒で2、3人が配属になることが多いのですが、自分の年は僕だけで。いわゆる新人仕事がだいたい自分に回ってくるのは大変ではありました(笑)。正直、週刊現代をちゃんと読んだことがなかったので、まずは読むところからでしたね。読者と自分では年齢の乖離もありますし、最初はどうしようと思いました」
3年間、グラビア班にて写真記事のページを担当。女優インタビューはもちろん、グルメや鉄道など、さまざまなジャンルの記事を担当したという。
「編集部に入ってすぐに政権交代があり、勝ちが決まった民主党の様子をホテルのパーティ会場で撮影に同行したりしましたね。入って2年目に東日本大震災が起こったので、地震から5日目に現地にカメラマンさんと入って、取材をしたりもしました」
写真週刊誌とマンガ。一見あまり関連がなさそうに見えるが、週刊現代で過ごした3年間の経験は「すごい財産になった」と語る。
「具体的には、人に話を聞くことに、なんのためらいもなくなりました。週刊誌の取材なんてためらっている場合じゃないので、いろんなことを聞けるようになりましたね。取材のノウハウを教えてもらったことも大きいです。マンガでも、例えばお仕事もので詳しい人に話を聞きに行ったりすることがありますが、周りの編集者と比べても自分は、取材へのハードルが低いなと思います」
当時の編集長に言われた言葉を今も大切にしている。「面白いって簡単に言うな」。
「『編集者の面白いって重いんだよ。せめてお前は本気で面白いと思っていないと話にならない』と言われ、本当にそうだなと思いました。自分が面白いと思ってないものを読者に出しちゃダメだというのはその通りで、編集としての根幹を教えてもらったと思います」
大学から大学院にかけて時間を費やした研究も、仕事に役立っているという実感がある。
「講談社の中だと、理系出身の人は多くはありません。理系の環境にいると、ものごとの根拠を求めることや、筋道を立てた論理的な説明ができることが強く求められるので、記事を書く際の『これって本当に事実?』と確認する姿勢も含めて、そうした経験は役に立っていると思います」
モーニング「きのう何食べた?」「インベスターZ」からの学び
年に一度、講談社では異動希望調査がある。もともとマンガ編集を希望して入社したものの、寺山氏は、1年目と2年目は異動希望を出さなかった。
「せっかく週刊現代に来たので、何かしらは役に立たないとと思い、3年くらいは噛り付きたいなと。結果的にお世話になったことのほうが多いですが、3年経った頃にそろそろマンガに行きたいと思って異動希望を出して、それが叶う形となり、モーニングに行きました」
編集者とひと口に言っても、週刊誌とマンガ誌では仕事が大きく異なる。
「週刊現代は毎週違うものを作っているので、いろんな種類のものを走らせながら、今出せるものはこれ!という形で出していきます。一方、マンガは積み上げていくものなので、作戦の立て方が全然違いましたね」
最初に担当したのは、なかいま強「ライスショルダー」と、よしながふみ「きのう何食べた?」であった。
「両作品とも、サブ担当という形で入りました。『ライスショルダー』は雑誌人気がとても高い作品で、いつも雑誌アンケートのトップ3に入っていた記憶があります。ネームの時点ですごい迫力があり、そんな作品に自分がとやかく言えるのだろうか、と不安はありました。とはいえ、自分なりにボクシングのネタを集めては作家さんにメールで送ったりして、たまにそれがヒントになって作品に反映されているとちょっとうれしかったり。自分、実はスポーツをまったく見ないのですが(笑)」
「ライスショルダー」は、「わたるがぴゅん!」のなかいま強による作品で、2007年からモーニングで連載され、2013年に完結。全18巻まで単行本が発売された。体格に恵まれすぎた18歳の少女・おこめが、ボクシングで世界に挑むスポーツコメディだ。なかいまの持ち味である小気味よい軽快なギャグと、キャラクターの愛らしさ、豪快なストーリーで多くのファンを獲得した。
その一方、よしながふみとの打ち合わせも刺激的だったという。
「よしながさんにはすでに2人担当がいて、自分も勉強のために 3人目として担当させていただきました。打ち合わせがすごく面白くて、最近どんな料理を作ったとか、この時期だからこういう料理を出せるといいですね、とか話したり。自分も料理をすることはあったので、作ったものや食べて美味しかったものを共有して。そうした、まるで雑談のような打ち合わせをするんですが、その後ネームになったときに、その打ち合わせで出た面白い話が完璧に盛り込まれた物語になっているんです! すごいなと思いました」
さらに、この時期に担当した「ドラゴン桜」の三田紀房の仕事ぶりも印象的だったという。
「三田さんの『インベスターZ』を、先輩編集である佐渡島庸平さん(現コルク)と一緒に担当させていただいていました。三田さんは本当にすごい! 『インベスターZ』は投資をテーマにした話で、ネタの面白さも突き詰められていますが、それだけではなく三田さんはキャラクターのことをすごくよく考えていて。例えば、あるネタを入れるためにキャラクターに無理な動かし方をさせてしまうと“キャラが死ぬ”、といったことをすごく気にされていて、なるほどと思いました。
自分はついついネタの面白さに引っ張られがちですが、キャラクターがなぜ大事かということについてハッとさせられました。認識のアップデートをいっぱいさせてもらいました」
佐渡島氏を始めとした編集の先輩からは「秘技」を盗もうと奔走した日々だった。
「どの先輩にもすごいところがある。例えば佐渡島さんは0→1を作るというより、1→100にするのがめちゃくちゃうまい方。たくさんコラボするなど、佐渡島さんが担当する作品は広がる力が半端ないんです。当時って、雑誌の売上がちょっとずつ落ちてきていた時代なので、そうなるとまず読んでもらうためどうするかという意識が大事で、そうした姿勢を学びました。
ほかにも、たくさんヒットを作っている編集者がどうやって打ち合わせをしているのか気になって仕方なかったので、教えてもらうために日々飲みに誘っていました。編集部はみんな忙しいのですが、飲みに行ったら 2時間くらい拘束できるので(笑)。いろいろ秘訣を聞きましたね」
「コンプレックス・エイジ」──なぜ描きたいのか?を突き詰める
熟練の作家、編集者のもとで学ぶ日々を積み重ねたのち、メイン担当として作品を立ち上げるようになる寺山氏。最初に単行本になった作品は「コンプレックス・エイジ」(佐久間結衣)だった。
「佐久間さんは、モーニングの新人賞に読み切りを投稿してくださって、自分にとって最初に担当した新人さんでした。もう一度読み切りを描きましょうとなったとき、佐久間さんは『コスプレのマンガを描きたい』と。とはいえ『好きだから描きたい』というだけでは理由としては弱いので、『コスプレの何が描きたいのか?』についてずっと話し合っていました。
そんなある日、原宿で打ち合わせをしていると、ゴシックロリータの格好をした人が歩いていました。それを見て、『あの人たちは、年齢を重ねるとどこへ行ってしまうんだろう』という話になり、『そこなんじゃないかな!』と思いました。つまり、もし自分がすごく大事にしている趣味と年齢を天秤にかけるような事件が起きたときに、人間ってどうなるんだろう?と。そうしたテーマで、読み切り版の『コンプレックス・エイジ』を描いていただいたところ、ちばてつや賞の一般部門で賞をとることができたうえ、Webに掲載して1、2カ月したところで突然バズったんです。その瞬間、これはいけるなと思って連載に向けて打ち合わせし、描いていただいたのが連載版の『コンプレックス・エイジ』です」
そんな経緯で始まった「コンプレックス・エイジ」は2014年から連載され、2015年に全6巻で完結した。主人公は、女児向けアニメ「マジカルずきん☆ウルル」が大好きで、キャラの再現度にこだわったウルルのコスプレを作ってなりきることに人生をかける26歳の派遣社員・渚。年齢を重ねて人生のステージが変わることで、趣味との付き合い方はどう変わっていくのか、というテーマに向き合った作品だ。コスプレという際立ったテーマに加え、オタクにとって切実な岐路をめぐる描写が多くの読者の胸に刺さり、話題となった。
「単に“コスプレのマンガ”というだけだと、コスプレが好きな人しか集まってこないんですよね。それだとやっぱり狭いし、せっかく描いていただくからにはたくさんの人に読んでほしいので、そこにつなげるにはどうすればいいの?というところまで掘り下げます。そこが掴めないと、ふわふわした話になるんですよね」
「これが描きたい」という主題だけでは不十分で、「なぜ描きたいのか」という作家の奥深くにある動機をあぶり出すことが大事だという。そのために、とにかく会話を重ねる。
「とことん聞いてみた結果、描きたいものが見つかればいいですし、よくよく考えるとただの個人的な好みであって、『描きたいものは特にないです』という場合は、それだけだとちょっと狭いのでは、という話をします」
こうして、読み切りから連載の形に仕上げることができ、さらに初めてメインで担当した作品がヒットし話題になって、ホッとしたという。
「週刊誌から来たので、マンガ編集としてちゃんと働けるぞと示さないとマンガ編集を続けられないと思っていたので、すごくプレッシャーを感じていたんです。そんな中で、1巻はおかげさまで発売即重版がかかったので、すごくうれしかったですね。
やれることは全部やろうと思って、1話目に登場するコスプレ会場のシーンでは、具体的な作品でコスプレを描いてもらうことにしました。『進撃の巨人』や『ダンガンロンパ』、初音ミクの会社にも許可取りをしたり。少しでも、とにかく多くの人が読んでくれる機会を増やそうといろいろやっていたことを思い出します。大変な思いをして描くのは作家さんなので、こっちは描けないかわりにせめてやれることはやりたいと思いました」
作家の描きたいものがきちんと描けているか?
こうして、編集者としての経験が積み重なっていく。この時期、中でも印象的だったのが、自分が読者として愛読していた作家に会いに行ったことだった。
「島田虎之介さんや黒田硫黄さんなど、自分が読んでいた作家さんとお仕事できたことはやっぱり印象に残っていますね。週刊現代の頃からいつかマンガ編集の仕事をしたいと思っていたので、いろんなイベントに潜入しては作家さんに名刺を配ったりしていました。例えば、蛇蔵さんには、週刊現代のときにご挨拶し、モーニングで描いてもらうことができたのが『天地創造デザイン部』や『決してマネしないでください。』でした。アックスでは島田虎之介さんが好きだったのですが、モーニング時代にご縁があって、『ロボ・サピエンス前史』という作品を描いていただきました」
どんな作家を担当する場合でも、作家の中にある“一番面白いもの”を引き出すために、寺山氏が心がけていることがあるという。
「『あなたのここがいいと思って担当を希望しました』ということをまず伝えます。担当させてもらおうと思ったということは、その作家さんの好きなところが自分の中に1個はあるはず。『ストーリーが素晴らしい』『演出がめちゃくちゃ好き』『絵がめちゃめちゃいい』など。連載が始まっても、何があってもそれはずっと忘れないようにしています。それを伝えたうえで、『何を描きたいですか?』という話をします」
制作過程の折々でも「最初に感じた作家のいいところがなくなってしまってないか」「作家の描きたいものがきちんと描けているか」をチェックするという。
「作家さんの描きたくないものになっていたら絶対うまくいかないので。とにかく、最初に聞き出した作家さんの『描きたいこと』、そして自分が『いいと思ったところ』、その2つが間違いなく入っているか。そこは譲れない。それがないと、作品ができはしたけど、ふわふわしたわけわからない感じになる。
今も、どうするといい打ち合わせになるのか?とか、そんなことばっかり考えています。マンガ編集になって、最初はやり方も体系化できていないので、もっとふわふわした打ち合わせをしていたと思います。それだとやっぱり頼りないので、なんとかしていきたいなと思って仮説を立てて、今ある仮説はそんな感じというところです」
仮説と検証を繰り返し、編集術を磨き続けている寺山氏。自身の編集者としての「長所」と捉えているのは、「会話」と「正直さ」、そして「根拠」だ。
「『こういうのを描きましょう』という提案をするというより、作家さんの描きたいものを引き出そうとしているので、そこをしっかり聞くところでしょうか。あとは、嘘をつかずに、正直に話すこと。それだけですね。『この人、本当のこと言ってるかな?』って思われたら多分おしまいなので。『ここがいいと思ったんですけど、ここはちょっとよくわかんないです』と全部言っちゃう。最初にそれで嫌われちゃった作家さんはもうなかなか会えないですが、その方のお力には自分はどの道なれないと思うので、最初からそうしていますね。
それから、打ち合わせでネームに対して意見を言うときに、ちゃんと全部理由が言えるようにしておく。『ここ、なんとなく嫌なんですよね』みたいな伝え方になると、描くほうとしてはどうしたらいいかわからなくなっちゃう。週刊現代時代に言われた『簡単に面白いって言うな』の話につながっていきますが、『面白くない』というときには、理由が必要だと思っています」
「とんがり帽子のアトリエ」心を動かした白浜鴎の言葉
ならば、寺山氏の「面白い」をもう少し突き詰めたい。ネームを見るときに心がけていることは、「読んだときに自分の心が動いたかどうか」。
「どんなに絵がうまくても、心が動かなかったら担当しない。自分じゃない誰かが担当したほうがその作家さんは幸せだと思うから。なんでもいいんです。『絵は全然だけど、ネームがめちゃくちゃ面白いぞ』とか、『話は破綻してるけど、このキャラクターはすごい好きだ』みたいなこととか。心が動いたときにそのしっぽを捕まえて、『お前、どこが面白いと思ったんだ?』と自問して、整理するようにしています。この世にあるマンガには、端的に言うと面白いものと面白くないものの2つしかなくて、それは、自分の心が動くか動かないかなんです」
「とんがり帽子のアトリエ」の白浜鴎は、こんなふうに寺山氏の心を動かした。
「絵がすごいことに加えて、ご本人に『何が描きたいですか?』と聞いたときに、『自分はマンガ家になれると思わなかったけど、友達がマンガを描いているのを見たときに、『もしかしたら自分にもできるかも』と背中を押してもらった部分がある。だから、今世の中にいるであろう“マンガ家を目指したいけど、自分には無理なんじゃないかな”と思っている人の背中を押せる作品になれたらうれしい』と言っていたんです。
それを聞いたときに、『これは!』と心が動いたんですよね。白浜さんは絵の素晴らしさはもちろん、このモチベーションがあるなら、いい作品を作ることができると思いました。すごく多くの人の心に刺さるだろうと」
「とんがり帽子のアトリエ」は、寺山氏がモーニング・ツー時代に手がけたヒット作だ。魔法使いに憧れる娘・ココは、村を訪れた魔法使いが魔法をかける瞬間をのぞき見てしまう。その好奇心はやがて大事件に発展してしまい、運命が大きく変わっていく──という、魔法をテーマにした本格ファンタジー作品だ。細密画のような美しい絵から紡ぎ出される、緻密な世界観とストーリー、キャラクターの愛らしさが高い評価を得、全世界での発行部数は550万部を超えている。2016年の連載開始から9年目の今年、満を持してTVアニメが放送予定だ。「とんがり帽子」は、白浜にとって2作目の商業連載作で、その名を世界に知らしめた大出世作となった。
さて、編集者が自分の“面白い”に自信を持つには、どうすればよいのだろうか? ひとりよがりの“面白い”が、危険な場合もある。
「自分の“面白い”を世間と常に比較し続けることです。自分は面白いと思っているけど、周りはそうでもないというのは“個人的な面白ボックス”に入れるんですよ。一方で、これはみんなも面白いと思うぞっていうのは“汎用的面白ボックス”に入ります(笑)。個人的なものと一般的なもの、それをちゃんと分けておくことも大事だと思いますね」
そんな寺山氏が、面白さの基準を作るために日々実践していることがあるという。
「いろんな方法がありますが、例えば、Yahoo!ニュースでもなんでも、記事を読んで、『この話面白いなあ』と思ったのに全然コメントついてなくって、『あれ? これは世間的には大したことないのかな』と思ったり(笑)。
あとは、売れている作品を見て、面白くないと思ったものには『なんで跳ねたんだろう、何かあるはず』と考えたりもします。そうやって、自分の中にはなかったけど、こういう面白さってあるのかな、と考えて面白さを広げていきます」
「ダーウィン事変」作者の「売れたい」が引き金に
2016年からはモーニング・ツーの編集長を務めた寺山氏。現在はアフタヌーンに異動し、副編集長として日夜作品づくりに心血を注いでいる。アフタヌーンに異動してから手がけたヒット作の1つが、2020年に連載を開始したうめざわしゅんの「ダーウィン事変」だ。
同作は、人間(ヒューマン)とチンパンジーの間に生まれたハイブリッドである “ヒューマンジー”チャーリーの存在をめぐって巻き起こる事件を通して、生命、倫理、愛の根幹を問う超大作。舞台はアメリカ、人間以上に明晰な頭脳と並外れた身体能力を持ったチャーリーが、高校に通い始めたことにより事態が動き出す。動物の権利を過激なやり方で主張するALA(動物解放同盟)との戦いを軸に、差別やテロなど人類が抱える問題に、恋人である人間・ルーシーとともに立ち向かう「ヒューマン&ノン・ヒューマンドラマ」である。実際にチャーリーのような存在がいたなら、ものごとはこう進んでいくだろうなと感じさせる説得力をびしびしと感じさせる作品で、果たしてどんな想像力や知識の蓄積、そして好奇心があればこんな物語が紡げるのだろうと嘆息するほど、重厚でいて軽快な、超一級のエンタテインメント作品だ。
ここで、作者のうめざわについても少し補足しておきたい。うめざわは、「ダーウィン事変」以前からマンガ好きの間では知られた存在であった。ヤングサンデー増刊でデビューし、週刊ヤングサンデーで「ユートピアズ」、月刊!スピリッツ(すべて小学館)で「一匹と九十九匹と」などを執筆。2017年に刊行した短編集「パンティストッキングのような空の下」で「このマンガがすごい!」2017年オトコ編第4位にランクイン。人間の汚い部分もまるごと描写するような、ときにはシュールすぎるほどのリアリズムで、マンガ読みの心を惹きつけていた。個人的には、古谷実の作風が好きな人には読んでほしい、味のある作品が多い。
とはいえ、うめざわを一気にメジャーな存在にしたのは「ダーウィン事変」だった。「マンガ好きが好むマンガ家」から、「誰もが知るマンガ家」に押し上げたものはなんだったのかと聞くと、「うめざわさんが『売れたい』と思ったことです」との答え。
「最初に相談されたとき、『これまで短編集も出ていて褒めてもらえるんですけど、あんまり売れてなくて。売れるにはどうすればいいですか?』と言われたんです。そう思ってるなら大丈夫と思い、『じゃあ売れるためにどうするかという話をしましょうか』という打ち合わせになっていきました。とはいえ、うめざわさんが描きたいことをブレさせてほしいわけではない。そこは譲らないでほしいけど、それ以外のところは売れるようにシフトしていきましょう、という話をしました。
『ダーウィン事変』については、すでにうめざわさんがおおよそのストーリーを最後まで考えてくださっていたからこそ、かなり重厚で重い話になることはわかっていたので、“入れ物”を軽くしないとみんな疲れてついてこないと思っていました。つまり、キャラクターデザインの工夫や、アクションシーンが頻繁に入って、チャーリーが強いぞというのを爽快なドンパチでも見せる、など。なんならあまり考えなくてもシンプルに読める作りにしたほうがいいと思い、そんなふうなお願いをしました」
まさに敏腕プロデューサー。力のある作家を「売れさせる」ためにはどこをどう変えればいいのか。うめざわのQに対する寺山氏のAが見事にハマり、うめざわがうまく実行に移せた結果、今や単行本の累計発行部数は160万部を超え、TVアニメ化も控えている大ヒット作となった。
「すごくシンプルに言うと、作家さんの持っているものや才能はそのままでいいんですよ。自然に伸びていくし、そこがなくならないようにだけ注意しておけばいい。ただ、その作家さんが苦手なところをフォローしてあげたほうがいいだろうなと思っています」
「ダーウィン事変」では、人間とそれ以外の種との交雑やセックス、テロを繰り返す過激な動物愛護団体、反出生主義など、さまざまなタブーが登場する。それゆえ、編集者として気を配る部分も多いという。
「関連したニュースをきちんと見ることは心がけています。いろんなニュースをいろんな媒体で見るだけではなく、それに対してWebではどんなでコメントがついていて、Xではどう言われているのか。つまり、記事を見て、どんな人がどういう意見を持つのか考えるようにしています。あとは、意見が割れている問題がストーリーに関わってくるのであれば、どちらかの意見に寄りすぎて、極端で差別的な内容になっていないかはすごく気をつけています。作品をもってしてどちらか一方を徹底的に叩きたいわけでもないですし。
みんなが話していることって面白さがあると思うんです。そういう意味で、話題になっているテーマを怯まず扱うことは、誰もやっていない新しい作品になりやすいと思います。もちろんその分、気をつけます。『ダーウィン事変』は連載が始まった当初は、社内の法務部にもよく相談に行ったり、知見をもらったりしていました。なにせ、どんどん情報もアップデートされていくので、うめざわさんとも、打ち合わせのたびに『こんなニュースがありましたね』という話をして、世間の流れとズレないように気をつけていました」
同作には、「読み軸」が2つあると語る。
「あまり考えずにも読んで楽しいんだけど、読んでいるうちにいろんなことが頭に入ってきて、読者の中で考えが芽生えてくる。そうして読んでみると、別の側面も面白いなというふうにだんだん深くなっていく──そんなふうに読んでくれるとうれしいです。最初から全部深いと、入ってこれない方が多くなっちゃうので、そういう意味でちゃんとエンタテインメントになっているかというのは気をつけています」
なるほど、チャーリーとルーシーの恋の行方や、チャーリーと敵たちの対立構造に注目してシンプルに読むのも楽しいが、読んだあとにどうしても動物の権利のこと、最近のヴィーガン事情、最新のゲノム研究についてなど、今生きている世界との接点を調べたくなってしまう。「入れ物」は軽いが、知的な仕掛けが生きている稀有な作品だ。
マイナーをメジャーに引き上げるのがアフタヌーン
マンガでは、モーニングとアフタヌーンの2部署を経験している寺山氏だが、目指すものの違いはないという。
「持ち込みに来ていただいた作家さんに『アフタヌーンってどういう作品を求めてますか?』と聞かれるのですが、自分の答えは、『面白ければなんでもいい』です。しいて言うなら子供向けではないくらいで、本当にいろんな種類の作品がアフタヌーンに載っている。『アフタヌーンだからこういう方向に寄せてください』みたいなことを自分が言ったことはありません。
アフタヌーンはマンガ好きが好む雑誌だと言われていて、実際そうした方にいっぱい読んでいただいていると思いますが、僕としてはマイナーなものをメジャーに引き上げるのがアフタヌーンだと思っています。だから、マイナー誌だとか、マンガの好きなコアファン向けに作っているつもりはなくて、作家の持っているコアなものをどれだけ広げて世の中にぶつけられるか、という意識でいます。さらに、アフタヌーンは一番新しくて面白いものを載せています。『こんなマンガあったんだ!』って思わせたい」
そんな寺山氏が思う「ヒットの条件」とは、「作家の描きたいものと読者が読みたいものが合致していること」。そして、作品が売れるには、少なからず運もあるという。
「例えば『ダーウィン事変』は2巻が出るときぐらいまでは全然売れておらず、打ち切り一直線だったのですが、3巻が出る前にテレビ番組で取り上げてもらえることになったんです。即座に『ここしかない!』と思って販売部と相談して仕掛けを作り、それきっかけで読んでもらえるようになって……というところからじわじわと広がっていった。なので、面白ければ売れるわけではないですね。そういう意味でやれることはやったほうがいいと思います。ちなみに、きっかけとなった番組は、『川島・山内のマンガ沼』です」
麒麟の川島が「ダーウィン事変」を面白いと推したことで、世間の認知が広がったのだった。
新進作家・山嵜大輝の挑戦「カオスゲーム」/物語はこう変化している
近年、寺山氏が手がけた作品では、山嵜大輝「カオスゲーム」もホットな作品だった。不正を嫌う週刊誌記者・鈴木蘭は、懇意にしているカメラマンが不条理な殺され方をしたことをきっかけに、「求世会」という謎の宗教団体が糸を引く、“神×神”のルール不明・カオスなゲームに巻き込まれていく。超能力、未解決事件、裏社会、新興宗教といった不穏なエッセンスがたっぷりと盛り込まれた、オカルト好きにはたまらないサスペンスアクションだ。
山嵜は、読み切り作品「岸辺の夢」で、アフタヌーン四季賞2020年冬のコンテストにて四季大賞を受賞し、高い評価を得た新鋭作家だ。「岸辺の夢」「カオスゲーム」ともに、夢や胎内記憶、もっといえばユングの集合的無意識(人類の心の中に普遍的に存在するイメージ)を思わせる超自然な存在がキーワードとなっている。ダークで夢幻を感じさせるような独特の世界観が魅力であり、諸星大二郎や伊藤潤二好きにはおすすめしたい。「カオスゲーム」ではさらに、安野モヨコのキャラクターを彷彿とさせるパワフルで軽快なコメディタッチ、キャラクター造形の妙も感じさせ、技量の広さも見せつけた。
「山嵜さんが『とにかくオカルトを描きたい』ということで、それに対して、『わかりました。オカルト以外はエンタメに全振りしましょう』と言って始まったのが『カオスゲーム』です。海外からの翻訳刊行のオファーが複数あったり、面白かったという声をいくつもいただいたりしました。
山嵜さんは今新しい作品に取り組んでいるところです。ご本人は初めての連載だったので、やってみないとわからないこともたくさんありました。『カオスゲーム』の連載が終わったあと、山嵜さんは打ち合わせのたびに『次は売れたい』と常々言っていて、本当に素晴らしいことだと思います。やっぱり描いたら読んでほしいというのは当たり前、『売れたい』って『読んでほしい』なんですよね。そのために自分がやれることはなんでもやりたいなと思いながら打ち合わせをしていますので、新作も是非お楽しみに」
山嵜の作品を筆頭として、四季賞の受賞作は、ほかのマンガ誌の新人賞と引き比べても、面白さが別格だと感じることが多い。バズる確率も高いように思う。素朴な疑問、なぜ四季賞の受賞作は必ず面白いのか?
「アフタヌーンという媒体には幅広い作品を載せているため、描き手からすると自分の作品も載せてくれるのでは、と思ってもらえることが大きく、応募作が多いことも関係していると思います。あとは、連載している作家さんが面白いものをずーっと描き続けてくれていて、それが綿々と受け継がれていることで作られていったブランド力が大きい。それがあるからこそ、今なんとかなっていると思います」
受賞作によっては、投稿されてきた作品がそのままの形で受賞することも、あるいは担当がついてブラッシュアップしたうえで受賞することもあるという。
「投稿作がそのまま、という例は、自分の担当作家さんで言うと、山嵜さんもそうですし、『7人の眠り姫』を連載中のFiok Lee(フィオク リー)さんもそうでした。Fiok Leeさんは、実は唯一四季大賞を2度受賞している方です。1度目のあとしばらくマンガを描かなくなって、その後もう一度“野良”で投稿してきて再び大賞を獲りました。
作家さんたちが面白いものを描いてくださるおかげで、なんとかブランド力が下がらないようにしていただいています。今は結構な黄金期でもあると思っていて、連載作品のうち10作品以上の1巻の発行部数が10万部を超えているんですよ。こんな月刊誌ほかにはないんじゃないでしょうか」
編集者の心得&面白がる力を持続させるためには
寺山氏が思う「編集者の心得」は、「いろんなことを面白がること」。
「自分の好きなものを突き詰めるのは、どちらかというと作家のやること。なので、編集者はいろんな作家が持っているものに『面白いですね』と答えられる、キャッチボールの相手になってあげられることが大事だと思います。なので、いろんなところにアンテナを張るといいんじゃないかなと。
興味のないものでも、『みんなは好きって言ってるけど、自分は全然ピンと来ない。なんでみんなこれ好きなんだろう? とりあえずいろいろ読んでみるか』みたいな姿勢、つまり雑食であることは大事だと思います。でないと編集になったときにつらい。自分の『好き』を描いてくる作家さんに巡り合えるまで、待ち続けるしかなくなっちゃいますからね」
「好き」を広げるために意識しているのは、できるだけ誘いを断らないことだという。
「もともと好奇心は強いほうだと思いますが、『今度こういう催しのがあるので来てください』と言われたら、全然知らなくても、まず行ってみます。
この前、お誘いいただいて『うたの☆プリンスさまっ♪』のライブに行ったんです。女性ファンが多い、サイリウムをいっぱい振るような感じの。自分はおそらくファン層からは外れているんですが、行ったらやっぱり面白いんですよ。ファンサービスがすごくて、めちゃめちゃこちらが気持ちよくなるように作ってるなって思って興奮しました。知らないところに連れて行ってくれる人って、貴重だと思うんですよね。それでハマることもあれば、なおのことです」
「このムーブメントはあそこから」と言われる作品を
今後目指すのは、「このムーブメントはあそこから始まったよね」と言われる作品。
「例えば、『とんがり帽子のアトリエ』を立ち上げた頃って、連載中のマンガで売れている王道ファンタジー作品が今より少なかったんです。というのも、ファンタジーって描くのがすごく大変なんです。高い画力で、世界観に説得力を出さなきゃいけない。設定もたくさん考えなきゃいけないけど、説明ばっかりだと読むほうが億劫になっちゃう、つまり、非常に描き手の“マンガ力”が問われるジャンル。
とはいえ、『ハリー・ポッター』や『ロード・オブ・ザ・リング』などの映画はヒットしているので、ニーズは絶対あると思っていました。そんなときに白浜さんから案が出て、『これはパイオニアになれるな』と思いました。これからも、そういう作品をたくさん送り出せるといいなと思っています」
編集者になって16年。現在、アフタヌーンの黄金期を支えている寺山氏には、読者が求める物語やヒーローの変化はどう見えているのだろうか。
「少し前まで、『正しさ』をすごく求めるようになったと感じていました。要するに、主人公が『いい人かどうか』。『M-1グランプリ』なんかを見ているとわかりやすいですが、数年前から“人を傷つけないお笑い”のムーブメントがあって、その流れがマンガ界にもあったんです。『いい人』がいて、読む側を気持ちよくさせてくれる。ですが、これは日々変わるもので、『地面師たち』のヒットで流れが少し変わった気がしています。振り子のようなもので、『いい人』が流行ると、次は『悪い人』の物語が読みたくなるんですよね。あるいは、わかりやすいものが流行ったかと思ったら、ちょっと難しいものが流行ったりとか。
我々は、次何が来るかを予測しておかないといけない。今流行ってるものを作るだけでは、結局列の中盤から最後尾の方になっちゃう。それよりは先駆者でいたいので、いつも0.5歩先を予想して、『次は何が来るかな?』と考えながら作っています。今後、具体的にどう変わるのかの予想に関しては……企業秘密ということで(笑)」
寺山晃司(テラヤマコウジ)
1983年、東京都生まれ。早稲田大学大学院生命理工学専攻卒。2009年に講談社に入社し、週刊現代編集部、モーニング編集部を経て、現在は月刊アフタヌーンの副編集長を務める。担当作品は「とんがり帽子のアトリエ」「天地創造デザイン部」「ロボ・サピエンス前史」「ダーウィン事変」「天国大魔境」「空挺ドラゴンズ」など多数。
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG